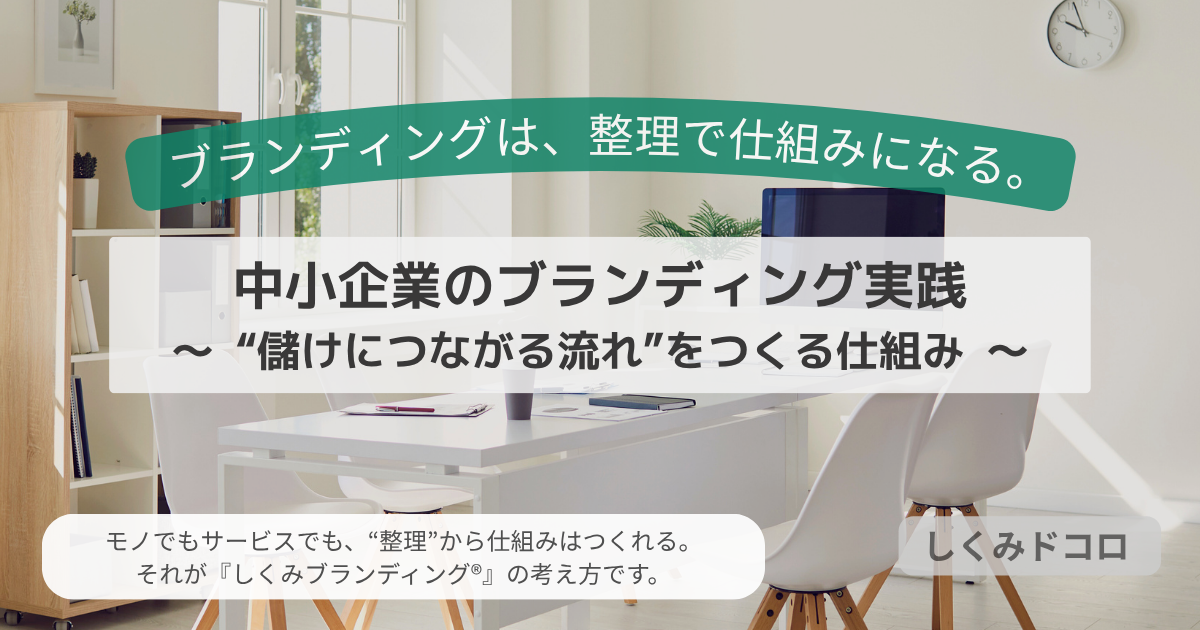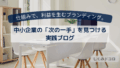はじめに|ブランディングは「仕組み」で動かす時代に
こんにちは。ブランディングディレクターの松本カヅキです。
ロゴやデザインを整えるだけでは、売上は動きません。
でも「お客様とのつながりの流れ」をちゃんと作ると、ブランディングは“儲けを生む仕組み”になります。
この記事では、実際の現場で結果が出た中小企業の取り組みをもとに、
ブランディングを“続けられる形”にする5つのステップを紹介します。
👉 ブランディングの全体設計から整理したい方は:
中小企業のブランディング戦略|整理から実践へつなげる設計法
“整理”を起点に、現場の流れを実践につなげる5ステップを解説しています。
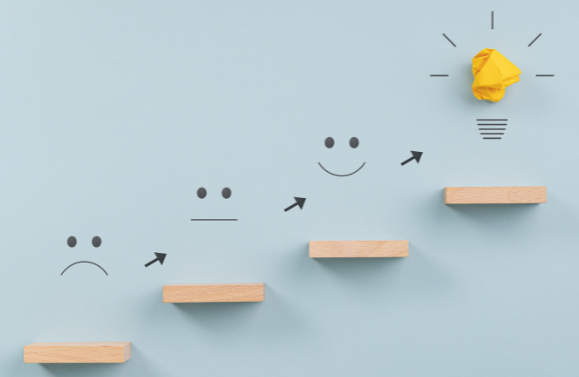
Step1|自社の強みを「使える形」に整理する
「うちの強みは何?」と聞かれても、すぐに答えられないことがありますよね。
でも、答えはいつも日々の仕事の中にあります。
- お客様に褒められたこと
- 他社ではやっていないけど、うちでは“当たり前”にやっていること
- ずっと大事にしてきた想い
これらを整理して、どんな場面で役立つかまで落とし込むのがポイント。
たとえば、「営業ではこれを伝える」「SNSではここを出す」と決めておくと、スタッフ全員で動きやすくなります。
Step2|お客様に届く“ひとこと”をつくる
強みを見つけても、それが伝わらなければ意味がありません。
伝えるためには、「誰に」「どんな良さを届けたいのか」を一文で表すことが大切です。
たとえば──
「忙しい朝でも3分で整うスキンケア」
「地域で一番“安心”を感じる整備工場」
難しいコピーを考えるよりも、相手の生活がどう良くなるかを伝えるのがコツです。
この一文をスタッフ同士で共有すると、どの発信にも“ズレ”がなくなります。
Step3|お客様が“出会ってから選ぶまで”の流れを整える
SNS、ホームページ、店頭、口コミ…
お客様が出会ってから購入・契約するまでの流れを一度紙に書き出してみましょう。
「どこで知って」「何を見て」「どう行動するか」を整理すると、
“どの部分を直せば売上が上がるか”が見えるようになります。
たとえば、ある食品ブランドではLP(紹介ページ)の流れを見直しただけで、
成約率が約2.3倍に改善しました。
💡 ブランド全体の流れを“しくみ”として設計する方法は:
中小企業のブランディング戦略|整理から実践へつなげる設計法
「価値の流れ」を整理し、成果につなげる実践ステップを紹介しています。
Step4|“伝わる言葉”に整える
ブランディングは「どう伝えるか」で成果が変わります。
たとえば、多種類展開のマウスウォッシュの商品で──
(A)「いろんなフレーバーのマウスウォッシュ!」
(B)「毎日、息を着替える。」
このたった一行をAからBに変えただけで、購入数が約5倍に増えた事例があります。
伝えるときは「お客様の気持ち」を主語に。
「私も使ってみたい」「自分のことだと思える」
そんな言葉に整えると、心に届きます。
Step5|“買ったあと”のつながりをつくる
ブランディングは、買ってもらうまでではなく“そのあと”が本番です。
たとえば──
- 購入後1週間以内に「使いこなしメール」を送る
- 1か月後に「次に役立つ提案」を届ける
- SNSやニュースレターで“また思い出してもらう”仕掛けを入れる
こうした小さな積み重ねが、リピートや紹介につながるブランドの流れになります。
実践事例
- 美容サロン:サービスの魅せ方を整えたことで予約数3倍
- 食品ブランド:ページ導線を見直して成約率2.3倍
- 日用品ブランド:言葉を変えたことで購入数5倍
どの会社も、難しいマーケティングではなく、
「お客様との流れを整えた」だけで結果が出ています。
よくあるつまずきと解決のヒント
よくある悩み 解決のヒント
| どこから手をつけていいかわからない | Step1「強みの整理」から始めてみる |
| 伝えたいことが多すぎてまとまらない | Step2・4の“ひとこと”を決める |
| 続かない・仕組みが定着しない | Step5の“リピートの流れ”を作る |
👉 ブランディングの全体設計を整理したい方はこちら:
中小企業のブランディング戦略|整理から実践へつなげる設計法
“整理”を起点に、実践で成果を出すための5ステップを解説しています。
まとめ|ブランディングは「続けられる仕組み」から育つ
ブランディングとは、派手な広告でもデザインでもなく、
日々の仕事の流れを整えることです。
- 強みを見つけて整理する
- お客様の気持ちに沿って伝える
- 買ったあともつながりを続ける
この3つを実践できれば、ブランドは自然に“動き出します”。
👉 ブランディングは、見せ方より先に“整理”が重要になります。
まず土台を整える方法は → [整理からはじめる実践ブランディング戦略]
💡ブランディングを“しくみ”として動かす第一歩を。
まずは、自社に合った“仕組み化の形”を一緒に整理してみませんか?
👉 [無料相談はこちら]
しくみブランディング®|松本カヅキ