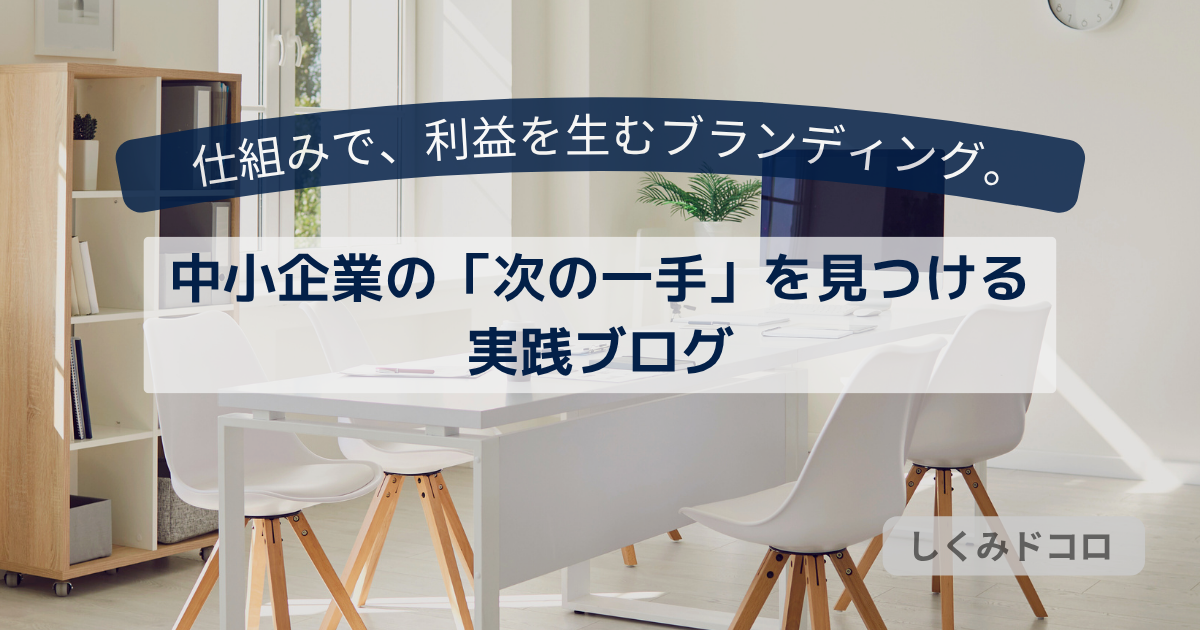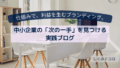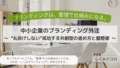はじめに
こんにちは。ブランディングディレクターの松本カヅキです。
最近、日本の中小企業の現状について深掘り調査をしてみました。
日々、いろいろな企業さんとお話ししている中で、
「がんばっているのに成果が安定しない」
「広告をやめたらすぐ反応が落ちる」
そんな声をよく耳にします。
調べていくと、数字や事例から見えてきたのは──
ブランドづくりと同じくらい、“仕組み”の存在が業績に影響しているという事実でした。
詳しくは「中小企業のブランディング|儲けに直結する仕組み化の方法」でも解説しています。
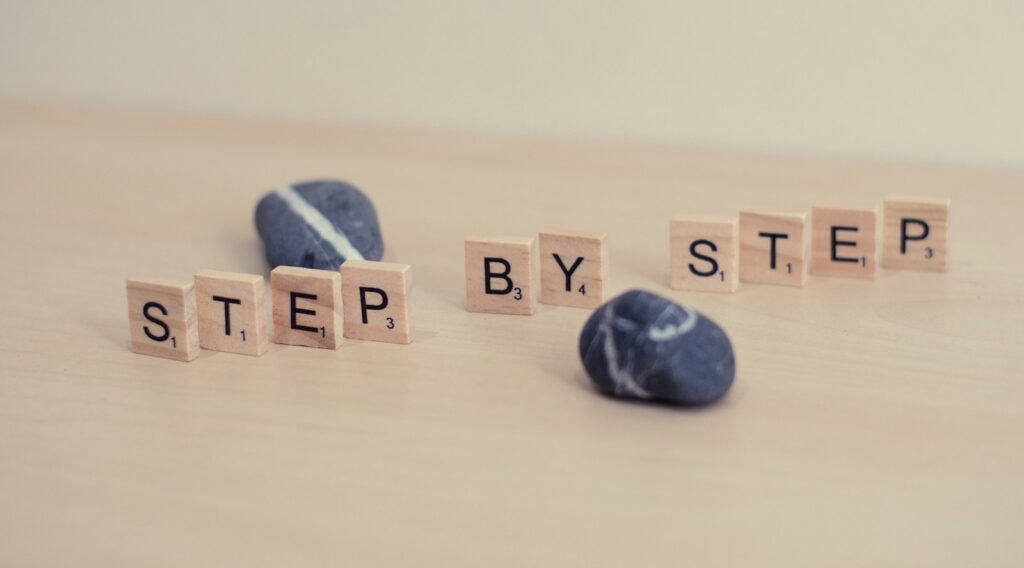
日本の中小企業の特徴と現状
圧倒的多数を占める存在
日本の企業の99.7%は中小企業です。
そのうち84.5%は従業員20名以下の小規模事業者で、地域密着型や専門特化型のビジネスを展開しています。
中小企業は地域経済や雇用を支える大きな存在である一方、規模が小さいからこそ抱える課題もあります。
主な構造的課題
- 人手不足:2024年上半期の「人手不足倒産」は過去最多ペース。物流業・建設業では約7割が人材不足。
- 価格競争:原材料・人件費の高騰を「十分転嫁できた」企業は17.4%。16%は全く転嫁できず利益圧迫。
- 属人化:4社に1社が「業務知識の属人化」を課題に挙げ、担当者不在で業務停滞のリスク。
これらの背景には、売れるプロセスや顧客接点が人に依存しすぎている=仕組み化不足があります。
結果として、価格以外で選ばれる理由を安定的に発信し続けることが難しくなっています。
この「選ばれる理由」を整理するヒントは「中小企業のブランディングは“目利き”で整う」にもまとめています。
市場環境の変化とブランドの必要性
販路の多様化と課題
コロナ禍を経て、
- EC化率:中小企業全体で23.4%
- 越境EC:2024年には半数超が取り組み
一方で、SNSやデジタルマーケティング活用企業は4割程度にとどまり、6割近くは未活用です。
販路は広がったものの、それを動かす仕組みを整備できていない企業が多いのが現状です。
単発施策では限界
広告やデザイン刷新など、単発の施策では長期的成果を維持するのが難しい時代です。
ブランドは日常業務に溶け込み、自然に回り続ける状態になって初めて力を発揮します。
成功事例と失敗事例
成功事例1:小池精米店(東京・原宿)
顧客体験型の米販売という独自戦略を確立し、売上を3倍に伸ばしました。
価格ではなく「お米を楽しむ体験」で選ばれ、安売り競争から脱却。
成功事例2:霧島酒造(宮崎県)
『黒霧島』ブランドを全国展開し、売上を約7倍に拡大。
業界トップを11年連続で維持。単発広告ではなく、全国規模で回る販路と発信の仕組みが支えています。
失敗事例:ある大手家具販売会社
かつて高級路線で支持を集めていましたが、低価格路線への転換によってブランド価値が揺らぎ、既存顧客離れと業績悪化を招きました。
ブランド戦略の一貫性を欠くと、価格以外の選ばれる理由を失いやすくなる例です。
なぜ「仕組み化されたブランディング」が中小企業にマッチするのか
一般的なブランディングはロゴ・スローガン・広告表現に偏りがちですが、中小企業ではそれだけでは不十分です。
なぜなら、人材の入れ替わりや多忙な日常の中でも「回る」状態を作らなければ、ブランドはすぐ形骸化してしまうからです。
私が提唱している「しくみブランディング」は、
- 集客〜購入〜リピートまでの流れを属人化させない
- 日常業務の中で自然とブランド体験が積み重なる
- 人が変わっても同じ価値が提供され続ける
という状態をつくるアプローチです。
これは、日本企業特有の「地道な改善」「長期的な関係づくり」の文化にフィットしており、短期的な広告戦略よりも定着しやすい特徴があります。
まとめ
今回の調査からもわかるように、中小企業の課題は単なる販促不足や広告量の問題ではありません。
日常業務にブランドを溶け込ませる“仕組み”があるかどうかが、大きな分かれ目になります。
日本の中小企業には、もっと選ばれ続ける理由があるはずです。
その理由を形にし、長く機能させるための方法のひとつが、この「仕組み化されたブランディング」という考え方です。
参考:中小企業白書2024/帝国データバンク調査2023
💡 自社に合った「仕組み化されたブランディング」を設計しませんか?
初回無料のオンライン相談で、現状課題と方向性をご提案します。
👉 無料相談の詳細はこちら
しくみブランディング®|松本カヅキ