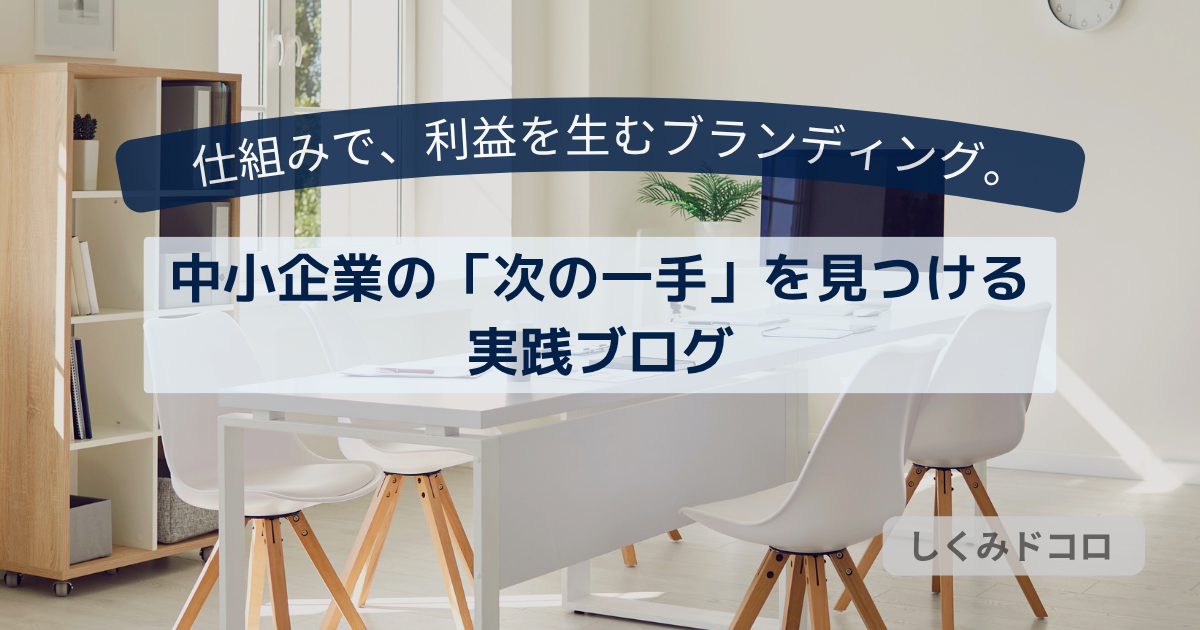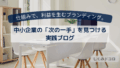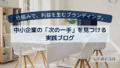「うちの強みって、言葉にはできたけど…結局どう活かしたらいいの?」
そんな声を、ブランディングの現場でよく耳にします。
ブランドづくりというと、かっこいいロゴや素敵なコンセプトを思い浮かべる方も多いかもしれません。
でも、いざ現場で動き出すと、
「そのブランド、どう育てていく?」という問いに立ち止まることが少なくありません。
そんな話をきっかけにあれこれと、“連載”という形でまとめてみることにしました。
「しくみドコロ」らしく、肩の力を抜きつつ。
でも、連載の中身はちゃんと“儲けにつながるブランディング”の話です。

「伝わらない」は、仕組みの問題かもしれない
たとえば、「地域密着型の誠実さ」を大切にしている会社があるとします。
その想いを社内で言語化し、タグラインやストーリーにまとめたところまではよかった。
けれど、
- ホームページではその言葉が埋もれてしまっている
- 商品やサービスには、その“誠実さ”が表現されていない
- 社員のふるまいとブランドの言葉にズレがある
……こうした状態では、「せっかくの強み」も、顧客には伝わりません。
✔︎ 現場から見えてきたリアルな事例
たとえば、あるウェディング関連のクライアントでは、
それまで受注の9割が「式場からの紹介」に依存していました。
しかし、「結婚式をしない」という時代の変化とともに、業績は次第に下降。
そんな中、彼らが取ったのは、“紹介されるのを待つ”のではなく、
現在のビジネスの“上流”にある「プロポーズ」のタイミングから価値を提案するというアプローチでした。
プロポーズという人生の節目において、“正装を着用する”というスタイル化や記念演出を提案し、
その流れから結婚式やドレスレンタルにまでつながる新たな導線を構築。
式を挙げないカップルにも“祝福のスタイル”を提案することで、
まったく新しい市場が生まれていきました。
これはまさに、言葉にした「価値」をビジネスとして活かす仕組みを設計した例といえるでしょう。
ブランドには「伝える仕組み」が要る
ブランディングとは、「言葉を整えること」だけではありません。
整えた言葉を“形”にして届けるための「仕組み」を整えることこそ、長く選ばれるブランドには欠かせない視点です。
- サービス設計やプランの構成
- 情報発信の導線とコンテンツ
- スタッフや現場でのふるまい
- 価格帯やパッケージの設計
こうした一つひとつに、「ブランドの意図や軸」が一貫して流れていること。
それによって、ブランドは“伝わるもの”として機能しはじめるのです。
『しくみブランディング』という考え方
私はこのような視点を『しくみブランディング』と呼んでいます。
“伝わる言葉”をつくるだけでなく、
“伝わり続ける仕組み”を設計し、運用していくこと。
- 強みを整理して
- 活かし方を設計して
- 運用まで支えるしくみを整える
そんなアプローチを通して、中小企業やスタートアップが“利益を生み続ける”ブランドを育てていく。
それが、『しくみブランディング』の考え方です。
▼次回予告
次回は、この『しくみブランディング』をどのように進めていくのか、
実際のステップに沿ってご紹介していきます。
「興味ある!」という方は、ぜひ次回もお楽しみに。
【しくみブランディング連載|第2回】利益を生み続ける!しくみブランディング実践5ステップ
\ 関連記事もおすすめです /
👉 ブランディングをどう“商売”に落とし込む?仕組みで実現する“儲かる型”
また、すぐにでも「自社の強みを見直して仕組み化したい」という方は、
【無料相談】も受け付けています。
お気軽にご相談ください~