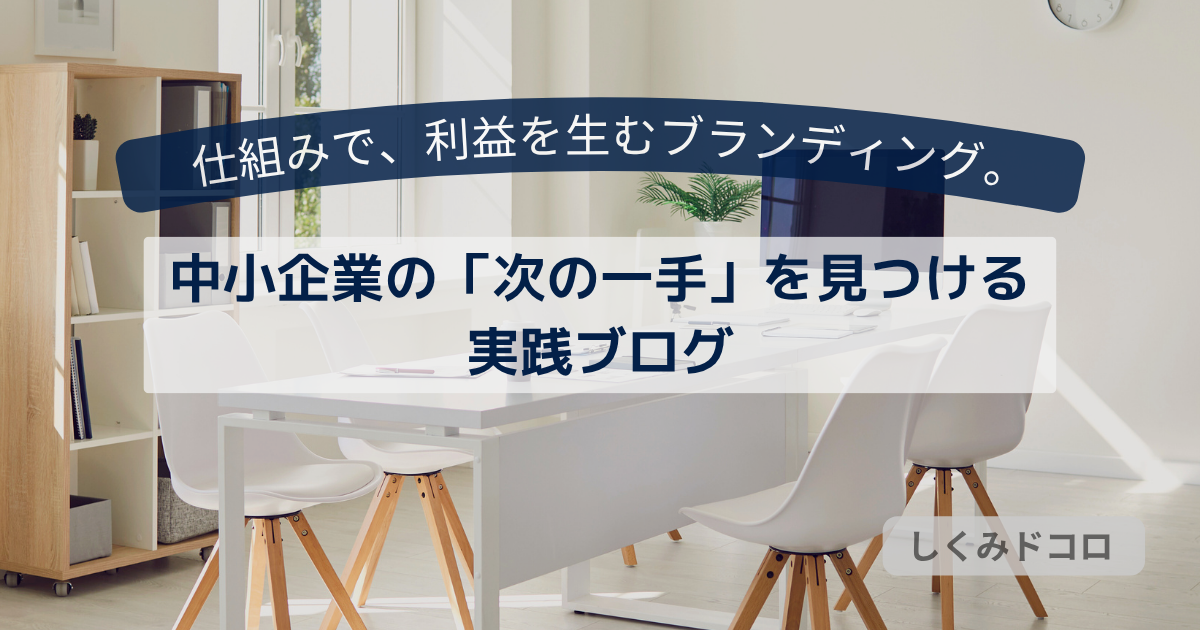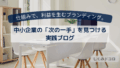思えば16年以上、なんだかんだ、ずっと「ブランディング」に関わってきて、、
企業・プロジェクト・商品やサービス・人・・
以上が主なブランディング対象として挙げられると思うのですが、
実際に、どんなブランディング推進にせよ、それらのプロセス全体を通じて、
やらないこと、削ること、を決めること。
というシンプルな意識をもっておくと、
比較的スムーズに推進しやすいなって思っています。
では、どんな“モノサシ”で、
やらないこと、削ることを決めていくか、
も大事かと思うので、
今回は、その“モノサシ”について、「しくみドコロ」らしく実践的に、あれこれと。

「ブランド・アイデンティティ」という言葉を聞いたことはありますでしょうか・・?
「顧客やターゲットに思われたいイメージ」
として定義されており、
現在のブランドイメージが「ブランド・アイデンティティ」とイコールとなる、
そうなるように推進していくのが、ブランディングである、
と多く定義されています。
そこで前述の、プロセス全体を通じてシンプルに意識する、
「やらないこと、削ること、を決める。」ということですが、
まずは、
「顧客やターゲットに思われたいイメージ」というモノサシから、
それに相応しているかどうか、
という観点で決めていくのがわかりやすいように思います。
少しざっくりした言い方をすると、
一歩先の将来像、というモノサシではかってみて、それに相応するかどうかで削っていく、
って感じです。
ただ、特に事業やサービスなど、
上記のモノサシでも、なかなかしっくりこなくて決めづらいな、という場合もあるかもしれません。
そんな場合、例えば、
日々、商品やサービスをカタチにして売って、という繰り返し活動をする中、
(人やお金を別として)
こだわりや特徴、ノウハウなど、
どんな“財”をずっと保有していきたいか、残していきたい“財”は何か、
というモノサシではかっていくとけっこう見えてきたりします。
いずれにせよ、
どんな“モノサシ”をもって、やらないこと、削ることを決めていくか、
そもそも、その“モノサシ”の設定自体が非常に大事で、しっかり議論して、
その“モノサシ”を認識共有していくプロセス、
これこそがブランディングの本質なのかな、とも思います。
あと、ブランディング推進の過程において、“削られたもの”についてですが、
すぐにストップしましょう、ということでもなく、
前面にはださないけれど、二番手以降に残しておいて、補完的、エビデンス的として活用する、
という場合もあるかと思います。
そういった感じで、区別して整理していって、
っていうのもブランディングの主な具体的作業だったりします。