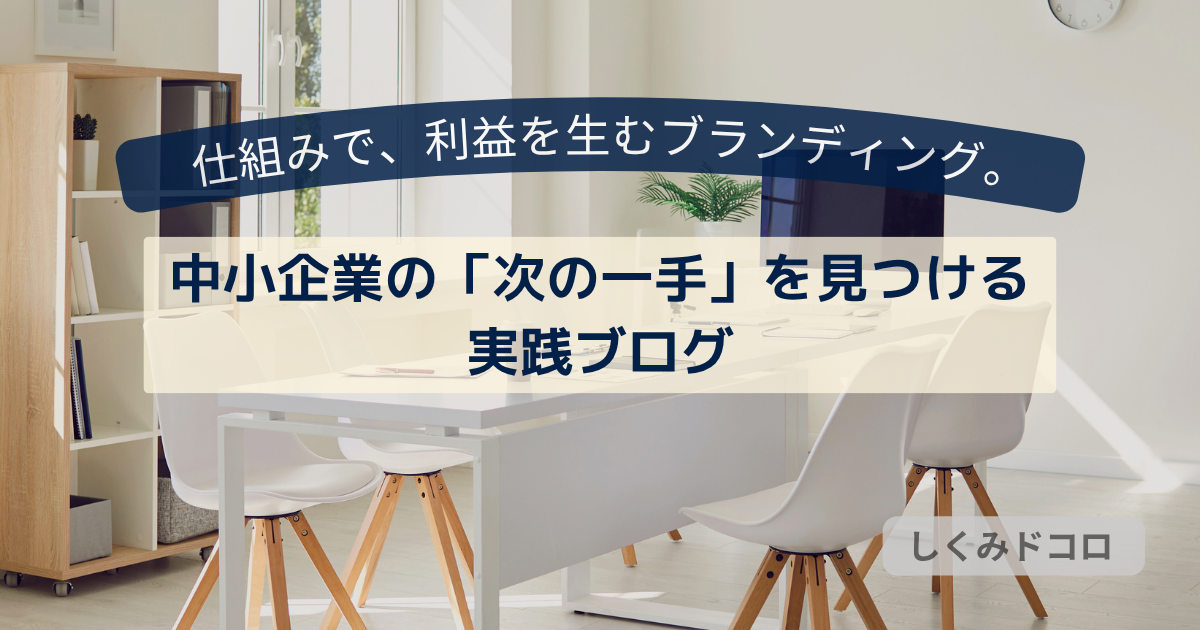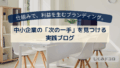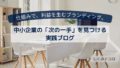売れる商品には、「売れ続ける」ための仕掛けがあります。
それは、単に商品が良い・パッケージが魅力的という話ではなく、
“店頭”と“ネット”の両方を視野に入れた導線設計ができているかどうか。
今回のVol.5では、これまでの「商品設計」「価格戦略」「商談設計」「営業導線」の続きを締めくくる形で、店頭導入後の販促施策とリピート導線について触れていきます。
「いい商品」だけでは回らない
最近の店頭を見ていると、
陳列された商品を手に取ったあと、スマホを取り出してネット検索する…そんなユーザー行動をよく見かけます。
つまり、「店頭にある」だけでは選ばれません。
その場でスマホを使って、口コミ・SNS・ブランドストーリー・価格比較など、
ネット上の情報と照らし合わせて“納得”して購入する人が大半になってきているのです。
このとき、商品に関する情報がネットに存在しない、または信頼できるレビューが見つからない、となると、せっかく店頭で気になってもそのまま棚に戻されることに…。
「口コミ」も、仕組みの一部
特にコスメ・雑貨系では、「口コミ」は“自然に広がるもの”ではなく、
意図して準備すべきプロモーション設計の一環です。
あるブランドでは、商品の公式情報とは別に、特徴成分に関するコラムを継続的に発信してもらったことで、「この成分ならここが詳しい」という立ち位置を確立し、ブランド認知の導線となりました。
また別の事例では、
「たくさんの強みを一度に伝えるより、まず一つに絞って打ち出す」
「その他の良さは、あとから“追っかけで”伝える」ことで、
商談やPOPにもストーリー性が生まれ、記憶に残りやすくなったという結果も。
口コミは、“共感できる誰か”の言葉を通して、「自分ゴト」にするプロセス。
それをあらかじめ商品企画や販促設計の段階から準備しておくのが、これからの商品展開において非常に重要です。
店頭×ネットの“回遊設計”が、売上を左右する
もうひとつ、大事な仕組みがあります。
それは、「知らないブランド」を「知っているブランド」にするための回遊導線。
たとえば、商品のパッケージやPOPにQRコードを設置してブランドサイトに誘導することで、
・その場で詳しい情報を補完
・SNSや口コミを確認
・ブランドの世界観に触れる
という流れが、スマホ片手に完結できます。
一方で、QRコードをECサイト直結にしてしまうと、「店頭で買わない人」が増えてしまい、
店頭回転率が上がらず、追加導入や販路拡大に繋がりにくくなるというケースも。
最初の目的は「店頭での購入」です。
その場で「買ってみようかな」と思わせる情報導線こそが、まず必要なのです。
テスト導入→回転率→拡大展開の流れ
リアル店舗のバイヤー商談では、多くの場合、
- まずは5〜30店舗でのテスト導入
- 一定期間後の「回転率」次第で更なる多店舗展開を検討
- さらに、問屋経由での横(他小売企業)展開も可能に
という流れが多いパターンです。
つまり、導入された店舗で“売れる”ことが何よりの営業材料になります。
特にバラエティショップでは、「他の導入店舗での売上実績」が、次の商談の決め手になることも多く、その意味でも、導入直後からの販促施策が非常に重要になります。
店頭は“入口”、リピートは“ネット”で
最後にもうひとつ。
最近の流れとして、リアル店舗での購入は「お試し」「発見」の場で、
2回目以降のリピートはECで買うというユーザー行動も増えています。
ですので、リピート購買までの導線として、
- パッケージやPOPで公式SNSやLINEへ誘導
- ブランドサイトからECや定期便へ案内
- SNSでコミュニティやコンテンツを充実
といった“ファン化”までの仕組みを整えておくことが、
長く愛用してもらう流れをつくるカギになります。
最後に|「売り場から逆算する」全体設計を
全5回にわたってお届けしてきた「商品展開・店頭導入ノウハウ」シリーズ、いかがでしたでしょうか?
本シリーズのテーマは一貫して、「売れる商品は、売り場から逆算する」ということ。
商品設計、価格戦略、商談、営業、そして販促とリピート導線まで。
一つの商品が、ブランドとして認知され、リピートされ、拡がっていくためには、
“商売としての全体設計”が必要です。
もしご自身の商品やブランドに、「仕組みとしての整理が必要かも」と思われた方は、
一度、無料相談をご活用ください。
“バラバラだった点”を“線でつなげて整える”ところから、一緒に考えていければと思います。
\あわせて読みたい/
👉 Vol.1 売れる商品企画とは?|売り場から逆算する考え方
👉 Vol.2 卸価格・利益の設計法|価格戦略の基本と注意点
👉 Vol.3 販路戦略と売り場設計|商談に進む準備のしくみ
👉 Vol.4 営業の仕組みを設計する|バイヤーに届く“話し方・資料・口コミ”の型