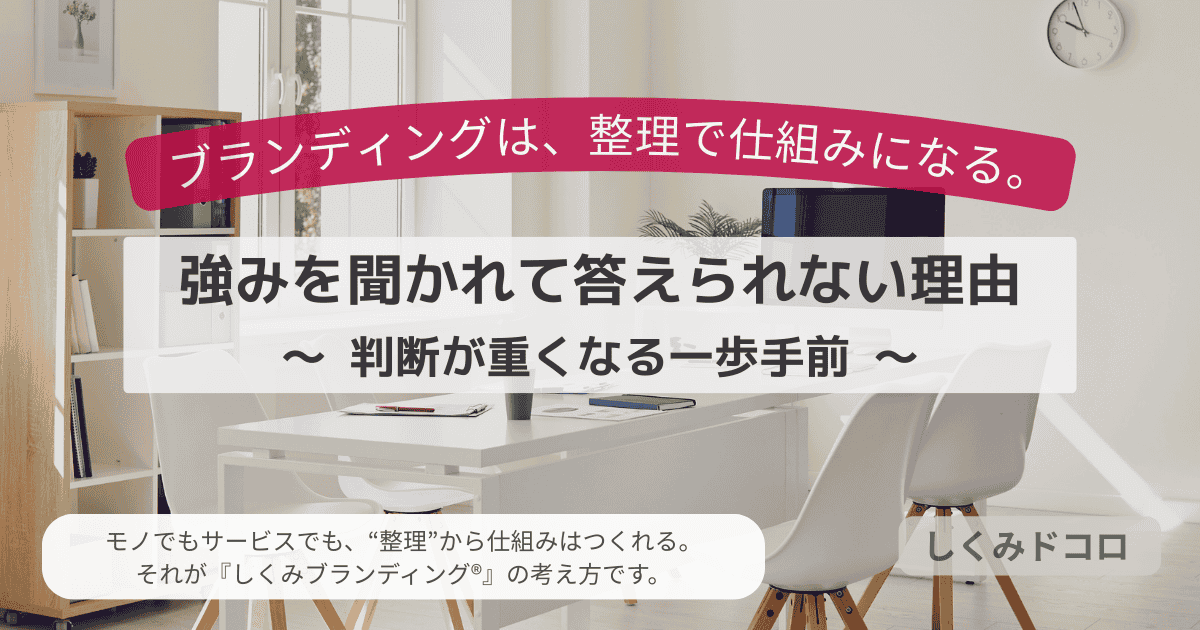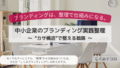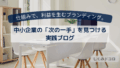判断が重くなり始めたと感じるとき
「あなたの事業やサービスの強みは何ですか?」
そう聞かれて、
すぐに言葉が出てこない。
それは、珍しいことではありません。
これまで、
「これはお客さんに喜ばれる」
「これは今やるべきだ」
「これは現実的に儲かる」
そう判断しながら、走り続けてきた。
結果として、事業は続き、売上もつくれている。
ただ、その判断の積み重ねがあまりにも多く、
あとから一言でまとめようとすると、
言葉に詰まってしまう。
でもそれは、
強みが無いからではありません。
むしろ、
どんな基準で選び、何を大事にしてきたのか。
その判断の中に、強みはすでに含まれています。
この「選んできた理由」を整理する視点を、
ここでは“目利き力”と呼びます。
無理に揃えなくていい。“選んできた理由”が残っている
事業やサービスが一つにまとまっていない。
商品や取り組みが多岐にわたっている。
それは、失敗ではありません。
地域の声に応え、
取引先の要望に応え、
その時々の判断で、現実的な選択を重ねてきた結果です。
その過程であなたは、
「何でも引き受けてきた」のではなく、
選びながら進んできたはずです。
ただ、その“選び方”を
一度も立ち止まって整理してこなかった。
その結果、
判断を迫られる場面で、
一つひとつの決断に、迷いが差し込むようになる。
ここが、
判断が重くなる一歩手前の状態です。
“理念スタート”ではなく、“判断スタート”で考える
多くの中小企業は、
理念やビジョンから始まった会社ではありません。
「これはいけそうだ」
「これなら喜ばれる」
「この話は現実的だ」
そうした判断の積み重ねが、
事業の形をつくってきました。
だから、
理念や強みを“先につくろう”とすると、
どこか噛み合わなくなる。
必要なのは、
新しい言葉を足すことではなく、
- なぜそれを選んだのか
- どんな基準で続けてきたのか
- 逆に、何を選ばなかったのか
こうした判断のモノサシを、
あとから整理していくことです。
それが、“目利き”という考え方の本質です。
目利きとは、特別なスキルではない
目利き力は、
特別な才能や専門知識ではありません。
日々の商売の中で繰り返してきた、
- 「これは違う」
- 「これは続けられる」
- 「これは大事にしたい」
そうした判断を、
あとから言葉にしていく行為です。
ここを整理しないまま戦略や施策を考え始めると、
判断は毎回ゼロから始まります。
逆に、
「自分たちは、こういう基準で選んできた」
という軸が見えてくると、
・何をやるか
・何をやらないか
が、自然に決まるようになります。
判断が重くなっているのは、
進めていないからではなく、
ここまで積み重ねてきたからこそ起きる状態です。
だからこそ、
次に進むためには、
新しい答えを探す前に、
一度、判断の前提を整理する必要があります。
この「判断の前提が整理されていない状態」を、
中小企業のブランディングにおける
“判断が重くなる一歩手前”として言語化したのが、次の記事です。
👉 中小企業のブランディングとは|次の判断が重くなる一歩手前の整理と思考
“目利き力”は、戦略の入口になる
目利きで整理されるのは、
答えではありません。
判断の前提です。
この前提が見えることで、
- 戦略を考えるとき
- 施策を選ぶとき
- 外部の提案を受けるとき
判断のたびに立ち止まらなくて済むようになります。
目利きは、
ブランディングの完成形ではなく、
戦略に入るための入口なのです。
整理 → 戦略 → 実践へ
“選んできた理由”を整理することは、
ブランディングの入口であり、
同時に、戦略を考えるための前提でもあります。
この判断整理を、
どの順番で戦略や実践につなげていくのか。
その全体像は、
以下の記事で整理しています。
👉 中小企業のブランディング戦略|整理から実践へつなげる5ステップ
まとめ|強みは、あとから言葉になる
強みは、
最初から用意されているものではありません。
走りながら、選びながら、
積み重ねてきた判断の中に、
あとから浮かび上がってくるものです。
「目利き」とは、
その判断を振り返り、
言葉に戻すための視点。
これまでより少し重く感じられ始めたとき、
一度ここに立ち戻ることで、
次の一手が見えやすくなります。
もし今、
「考え方は腑に落ちたけれど、
自分の事業に当てはめると整理しきれない」
と感じているなら、
一度、判断の前提を言葉に戻す場として、
こちらも用意しています。
👉(無料相談はこちら)
しくみブランディング®|松本カヅキ
― ブランディングは、整理で仕組みになる。 ―