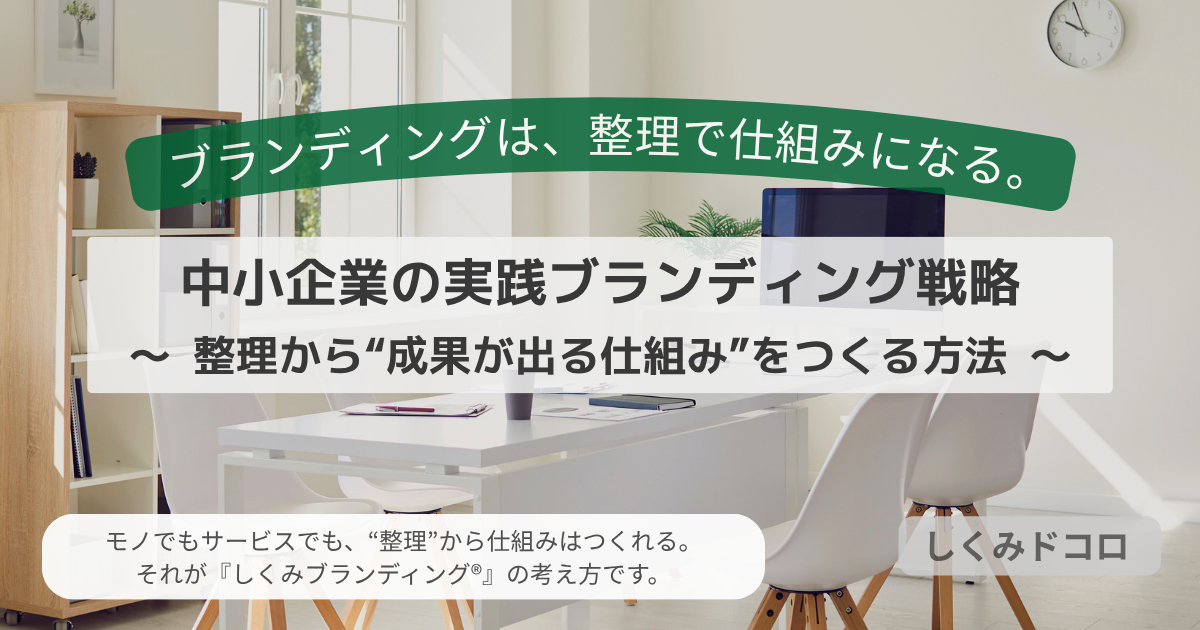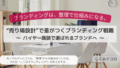中小企業のブランディングを“実践”で成果につなげるには、まず「整理」から。
こんにちは。ブランディングディレクターの松本カヅキです。
ブランディングというと、大企業や広告予算のある会社が行うものと思われがちです。
しかし、むしろ中小企業こそ、限られたリソースの中で成果を出すために“ブランディング”が欠かせません。
とはいえ、
「理念もロゴも整えたのに、なぜか成果につながらない」
──そんな声を、これまで200社以上の現場で何度も聞いてきました。
ブランディングには「まず強みを見つけることが大切」と言われます。
でも、いざ掘り下げようとしても、自問自答ではなかなか出てこない。
なぜなら、多くの中小企業は「理念スタート」ではなく「商売スタート」だからです。
地域のお客様の声、新しい取引先とのご縁、時代の流れ……。
目の前の機会に応じて柔軟に動いてきた結果、事業が増え、サービスが並列に走っている。
それは“柔軟に応えてきた証”でもあります。
ただ、いざブランディングを進めようとすると、情報や方針の整理が追いつかず、
「何を強みに据えるか」が見えなくなる。
そのまま制作や広告に走っても、成果に結びつかない。
──だからこそ、最初にやるべきは“整えること”。
つまり、「整理」です。

実践ブランディングの第一歩は「整理」から
ブランディングという言葉には、“作る”イメージが先行しがちです。
しかし実際は、“整えること”こそが最初の一歩。
経営の棚卸しをしてみると、
・事業が増えて全体像が見えない
・サービスごとの方向性がバラバラ
・理念やデザインが更新されていない
こうした「情報の散らかり」がボトルネックになっているケースが多いです。
まずは点在している要素を整理し、全体を貫く視点やテーマを見つけ直す。
そこから、“しくみ”としての流れを形にしていくことが、実践ブランディングのはじまりです。
特に中小企業のブランディングでは、この“4つの整理ステップ”が成果を分けるポイントになります。
① カサ構造ブランディング ― バラバラを“意味や価値”で束ねる
「結局この会社は何が強いのか?」
それを一言で言えないとき、まず取り組むべきが“カサ構造ブランディング”。
複数の事業や商品を、「誰に」「どんな価値を」届けているのかという共通の視点や軸で再定義します。
たとえば:
・複数の商品やサービスを「〇〇な暮らし方の提案」として束ねる
・多様なサービスを「地域に寄り添う支援」として括る
・商品群を「〇〇という体験をつくる手段」として捉える
こうして“意味や価値のカサ”を見出すだけで、
バラバラだった事業の関連性が見え、会社全体の「らしさ」が浮かび上がります。
👉 関連:中小企業のブランディング戦略|“カサ構造”で整える実践整理法
② 目利きブランディング ― “選んできた理由”を言語化する
いろんな事業や商品を展開してきた企業ほど、ブランディングのヒントは「なぜそれを選んできたのか」に隠れています。
過去に選んだ商品、取引先、サービス──そこには共通する“判断のモノサシ”があります。
それを言語化するのが、「目利きブランディング」。
「どんな価値を見出してきたのか」
「どんな理由で選んできたのか」
この2点を整理するだけで、“らしさ”が浮かび上がります。
理念を作るよりも、実践を振り返る。
それが中小企業にフィットする、現場発のブランディングです。
👉 関連:中小企業のブランディング戦略|“目利き力”で整える実践整理法
③ ハードとソフトを分けて整理する(店舗・サービス業向け)
店舗や施設など、リアルな現場を伴う業態では、
「ハード」と「ソフト」を分けて整理するのが鍵です。
ハード=立地・内装・設備・人員など(変えにくい要素)
ソフト=接客・体験設計・販促・メニューなど(変えられる要素)
創業時の「ハード×コンセプト」のまま走り続けてしまうケースも多く、なかなか変化に対応できず、ブランドが停滞します。
“変えられること”に注力し、“変えにくいこと”を見極める。
これが、停滞から抜け出す実践的なブランディングの突破口です。
👉 関連:店舗経営のブランディング戦略|ハード×ソフトの整理で再構築する方法
④ 体験価値ごとに整理し、「選ばれる理由」を見える化する
次に、顧客の体験視点から事業全体を見直します。
たとえば:
Before: サービスやメニューが羅列され、強みが伝わらない
After: 体験価値(共感・没入・創造など)の視点で整理し、提案力を高める
提供する内容ごとの単位で並べるのではなく、
「顧客がどんな体験を得るか」で構成し直すことで、
“選ばれる理由”が自然に伝わるようになります。
体験価値を基準に整理すると、
サイト構成や営業資料、社内教育まで──
あらゆる接点に一貫したストーリーが生まれ、
ブランドの流れがスムーズに整っていきます。
整理から“外注”へ ― 成果を出すための次の一手
ここまでの4つの整理軸を実践する中で、多くの中小企業が抱くのが、
「自社だけでどこまで整理できるのか?」という悩みです。
“整理”は単なる準備ではなく、ブランディングを仕組みとして動かすための設計段階。
だからこそ、ここを外部の視点と掛け合わせることで、成果が一気に加速します。
理念やデザインの前に、“整理”から外注できるパートナーを持つ。
それが、失敗しないブランディングの新しい進め方です。
👉 関連:中小企業のブランディング外注|“丸投げしない”成功する共創型の進め方と整理術
⑤ 整理を“リズム”にする ― 成果を出すブランディングは習慣から生まれる
整理は一度きりでは終わりません。
日々の商売が動くたびに、情報も現場も少しずつ変化します。
だからこそ、「整理を習慣にする仕組み」が必要です。
たとえば:
・月に一度、全事業の棚卸しをする「ブランドミーティング」
・新商品や新施策の前に「整理チェックリスト」で確認
・スタッフ間で「今の強み・弱み」を共有するリズムをつくる
こうした“小さな整理のリズム”があるだけで、
ブランドの軸はブレず、発信や判断の精度が上がり、成果につながる動きが生まれます。
整理を“習慣化”できる会社は、
ブランディングを“成果につなげられる会社”です。
整理を軸に据えた実践的なブランディング戦略は、
中小企業が“仕組みとして成果を出す”ための最短ルートです。
👉 次のステップへ進みたい方はこちら:
中小企業のブランディング戦略|整理から実践へつなげる設計法
整理で見えた価値の流れを、実践につなげるための5つのステップを解説しています。
まとめ|ブランディングは“整理”で仕組みになる
ブランディングは、新しく“作ること”ではなく、“整えること”から始まります。
全体を意味や価値で束ね、
自社の判断軸を言語化し、
顧客の体験価値で再構成する。
この3つを押さえるだけで、ブランドには“自然な流れ”が生まれます。
『しくみブランディング®』は、まさにこの“整理”を仕組み化するためのフレーム。
整理こそが、ブランディングを実践に変える第一歩です。
💡 無料相談のご案内
「自社にも“整理”が必要かもしれない」と感じた方へ。
まずは無料のオンライン相談で、現状の棚卸しと次の一歩を一緒に整理してみませんか?
👉無料相談はこちら
しくみブランディング®|松本カヅキ
― ブランディングは、整理で仕組みになる。 ―